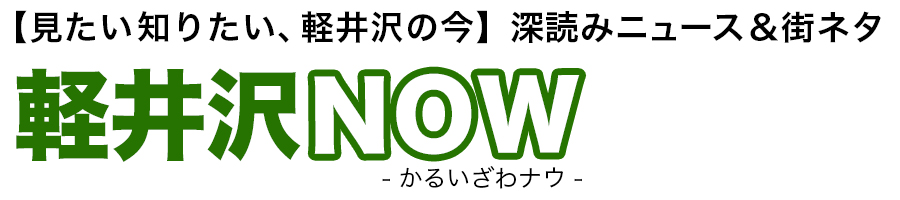あれから2年、まもなく3年。医学部でもなく、大学病院でもないところと提携したことによって、軽井沢町の2億5千万円という税金がいったい何に使われていたのか、町民にとっては未だ見えてこない使途不明金がある。その一端が今ごろ見えてきた。それはなんと、遥か南の島のために使われていた。
2年前の謎が解けました
S(佐藤) 意外なところから、とんでもないことがわかったのでお知らせしたいと思います。こちらのチラシをご覧下さい。

M(森) これは何ですか?
S 田村淳というお笑いタレントのイベントのチラシなんだけど、左上を見て。
M 信州大学社会基盤研究所って書いてある。
H(広川) これは前に下田さん(軽井沢の町長選挙に出馬し話題を集めた別荘住民)のXポストに出ていたチラシですね。右下には信州大学社会基盤研究所の丸橋教授が写真入りで出ています。
M 丸橋教授はこのイベントのコーディネーターをやっていたんですね。
H 下田さんも書いていましたが、プロフィールに「刑事告訴し、刑事告訴もされた経歴を持つ」なんて自己紹介文を書いていますよ。
M このチラシは信州大学社会基盤研究所が主催ですね。なぜ、丸橋教授が奄美大島なの?
S それが問題なんです。2023年3月の南海日日新聞に「信州大学法経学部の学生6人が奄美の歴史文化の知識を生かした黒糖焼酎の商品をプレゼンした」という記事が出ています。その中に、「丸橋教授が2年前から奄美大島を訪れて地域が豊かになるモデルを作りたいと企画した」と書かれています。「地域に根差して調査した成果が十分に発揮された。奄美大島の魅力増進につながる」と教授はコメントで自画自賛しています。
H 丸橋氏お得意の「地域おこしのための研究」というわけですね。
M もちろん、それが社会基盤研究所として利益を得るための目的なのでしょう。軽井沢の寄付講座の記者会見でも「私は(企業や行政から)お金を集めてくるのが得意なんです」と言っていたそうですから。
H この訪問研修は、大阪のウェルネスオープンリビングラボとの産学連携事業の一環で、奄美大島の酒蔵見学に行ったことを私も最近知りました。
S 問題は、この奄美大島への旅費が軽井沢の寄付講座、例の2億5千万円の不明な使用金に入っているということなんですよ。
M えぇ~!軽井沢の税金が…、そんなことに。
H 軽井沢新聞社が調べて判明した、2018年~2021年に信州大学が出しきた資料によれば「奄美大島の奄美観光ホテルに2021年2月10日~15日までの宿泊費が15万円、レンタカー3万円」という明細が出ていますね。2021年という年もぴったり合っていますね。この資料を見たときにはなぜ、奄美大島?と思ったけど、こういうことだったわけですね。
S 軽井沢の住民がこの寄付講座に不信感をいだいて町へ住民監査請求しましたが、その中でこの旅費も使途不明金として問題視されていましたね。「目的も結果も報告されていない」と。
M 軽井沢町民の血税を使って、まちおこし等と称して学生を動かして利益を得たというわけですか。
H 利益を得たかどうかはわかりませんが、旅費に軽井沢からの税金が使われたこことは確かですね。税金を払っている別荘住民や町民が知ったら、どう思うでしょうね。
(下の写真は奄美大島)

文科省から多額な補助金の「人材養成コース」、その結末は
H 私もその後、わかったことがあります。信州大学社会基盤研究所はとんでもない失態を演じていますね。ネットに出ている視察報告書を見てください。
S 以前、軽井沢NOWでも問題にした「ライフクリエーター人材養成コース」のことですね。
M 文科省から1億2千万円も補助金をもらったのに中間結果が6大学中、最低という恥ずかしい結果でしたね(詳しくは軽井沢NOWの過去の記事をご覧ください)。
H しかも恵シャレ―の敷地にある建物を購入して経費などやりたい放題。それなのに中間結果は散々でした。その文科省「知的集約型社会を支える人材育成事業」の更なる結果が出ています。
(写真は社会基盤研究所が購入した恵シャレ―のカフェの建物。その後、すぐに売却された)

M その事業は本来何を目的としているものなんですか?
H 文部科学省が「今後の社会の変化や展開に対して柔軟に対応しうる能力を有する幅広い教養と深い専門性を両立した人材を育成すること」を目的とした事業。日本学術振興会が評価を発表しています。令和5年度の視察報告書では、信州大学に対して次のような評価を出しています。
1.未だ履修者が少ない。2.未だ全学的なものとは言い難く、事務支援組織も十分に機能してない。3.申請時の計画調書に大きく打ち出されていた学外地域との連携についても、寄附講座の停止など不安要素を抱えており、今後の円滑な進展に大きな危惧が持たれるが、その点について大学側から十分な説明はなされなかった。4.また、本事業計画の特徴の一つであるファンドレイジング(学校法人などが活動に必要な資金を集めること)も、現状においては停滞しており、順調に推移しているとは言い難い。
など、散々の評価。この3とは軽井沢の寄付講座のことを指しています。
S それで、この養成コースはどうなったわけ?
H 結局、社会基盤研究所では運営が無理ということになり、信州大学が別途「ライフクリエーター人材養成事業戦略部会」を新設して、大学本部が積極的に関わり指導する体制へと変更したという報告がされています。
M なんというお粗末な結果!
S 大学本部がやることになって、学生にとってはかえった良かったのかもしれませんよ。